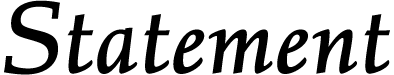「始めるのは事情、続けるのは意志」
僕は20代半ば、池田満寿夫の著書『模倣と創造』に出会った。その中にあった「始めるのは事情、続けるのは意志」の「事情」という部分に違和感を覚えた。おそらく始める理由にもっと確かな根拠のようなものが欲しかったのだろう。そして「始めるのは事情、 続けるのは意志」という言葉は、僕の創造行為の中での長い間の問いとなった。
他の人から、「何故石彫を始めたの?」と聞かれることがよくあった。僕はその時なりに、如何にも意味と意義があるような理由を捻り出し、話してきた。しかし50 歳が見えた頃、何度か読み返したカントの『純粋理性批判』とハイデッガーの『存在と時間』を自分なりに取り込めたと感じた時、その「事情」という言葉が僕の中にストンと落ちた。人は自分が知っていることの中からしか物事を選択することができないということ。まさに「事情」。簡単なことだった。
中途半端な進学校でダラダラと時間を過ごしていた僕は、特に行きたい大学もなく、たまたま美術の成績だけが「5」だったというだけの理由で美大進学を選んだ。初めは工芸を志望したけれど、そう簡単に大学に入れず、浪人を重ねているうちに工芸から彫刻に興味が移り、なんとか東京造形大学彫刻科に入学した時には 23歳になっていた。大学の石彫場には生涯お世話になることになる一人の教授と気のいい同年代の先輩が数人おり、そこで酒を飲み明かしているうちに自然と石彫を専攻していた。これらの事情の一つでも欠けていたら僕は石彫というカテゴリーには入っていなかっただろう。
さらに、制作を続けられたのも「事情」だった。
まずは大学2年生の時、偶然ありついた予備校講師というアルバイトがその後の僕の生活と制作のための資金を提供してくれることになったために、作品を生活の糧にする必要がなかったこと。これが最も大きかった。もう一つは、訳有りの50 坪の土地を破格とはいえ当時の僕らにとっては高価な土地を妻に買ってもらい、自分一人の制作環境を所有できたこと。もし月3万円の家賃でアトリエを借りて今に至っていたとしたら、5倍以上のお金がかかっていたことになる。
それでは、続けている「意志」は? これについてはなかなか言葉にすることができなかった。池田満寿夫の問いに答えることができていない。
僕は人に「職業は?」と聞かれると「教員」と答えていた。何故か自分の名刺の肩書きを「彫刻家」とせず「石彫」と表記していた。 これは僕にとって「彫刻家」とはあまりに高貴であり美しすぎるので、そうしているのだろうと自己判断していた。 また、デュシャンの著書『創造的行為』にある「芸術係数」という概念が僕の制作上の拠り所になっていた。
2019年個展の際、伊豆井秀一 氏 ( 元埼玉県立近代美術館主席学芸主幹 ) にコメントを依頼した。快諾してくれた氏は、僕の作品の根拠を探るため長時間の丁寧なヒヤリングをしてくれた。少年時代。父の故郷長野県小諸市の懐古園。あの石垣の古城に、何度となく連れられた時のことを語った時。自分が何に突き動かされているのか、突然気づいた。
僕は石と石が組み合う隙間に生まれる線に魅かれていたのだ。
石がうまく組み合ったり、積み上がったりした瞬間の快感。
とりわけ何も加工せず偶然にピタッときた時。その惚れ惚れする様な石と石との合わせ目の表情との出会いは、僕の心を天にも昇る歓喜の絶頂に導く。
この感じは、美を追求する芸術家が辿り着く境地とは明らかに違う。
これはかつての石工が日々の肉体労働の中で、時折感じていた喜びに近いものであるのではないだろうか。
僕がもしルネッサンス時代に生きていたら。ミケランジェロの下で働く彫刻家集団を志すのではなく、カラーラで石工となり妻が作ってくれる自家製の塩がきいた生ハム入りのパンを持ち、バチカン宮殿建造のための大理石採掘場に通う。毎晩ワインを楽しむ。夏の休日はマリーナで日光浴をしながらビールを飲んで妻と過ごす。生活は常に楽ではないかもしれないけれど、日々を精一杯生きる。そんな石工になることを望むだろう。
日本で今。本当の石工になれなかった僕は、制作という時間の中で意図してできなかったことと、意図せずできてしまったことの狭間を彷徨いながら、空想の石工となり自分が生きているという実感を楽しんでいる。
これが僕が出した「続ける意志」。
1959 年生まれで耳順など程遠い僕だけど、やっと池田満寿夫の長い間の問いに答えることができたと思っている。
樋口 恭一